
メンバー

松元 佳彦経営企画
SUPER STUDIOでは、社内表彰制度「SUPER STUDIO AWARD」を実施しています。全6回に渡り、2024年度の受賞者インタビューを紹介します。
第5回は、2024年度MVP バックオフィス部門を受賞した松元 佳彦(マツモト ヨシヒコ)さんです。インタビュアーは人事戦略室の吉田が務めました。

ーまずは、今までのキャリアと現在の業務内容について教えてください。
大学を卒業後、映像クリエイターとしてキャリアをスタートし、メディア企業で新規メディアの立ち上げや広告映像の撮影・編集に従事していました。同時にフリーランスとしてWebCMやモーショングラフィックスの制作も手がけていました。2社目に在籍していた会社は規模が小さかったため、主にメディア事業部の統括をしながら労務や採用、研修、評価制度の設計といった人事関連業務、日々の会計伝票点検や決算対応などの経理業務までバックオフィス全般に従事しました。そのような中でデロイトトーマツ ファイナンシャル アドバイザリー合同会社出身の上司との出会い、彼の類まれなる経営手腕に影響を受け、これが人生の転機となりました。3社目はその上司が転職したRevComm社に経営企画職として入社し、事業計画の策定や資金調達の支援、投資家・社内向け報告資料の作成、営業チームの成果管理やデータ分析支援を担当しました。
その後SUPER STUDIOに入社し、現在はセールス部門と連携してSalesforceの基盤改修やオペレーション改善を主導しながら、事業計画の作成や取締役会向け報告資料の作成など幅広い業務を担当しています。
入社の決め手はいくつかありますが、子育てに理解のある職場であったことと、経営企画を管掌している方の実務に対しての解像度が非常に高く、自らも積極的に手を動かす方だったことです。経営企画の業務に携わる以上、業務が増えたり変わったりすることは頻繁に起こり得ることなので、特にこの要素は重要であると考えていました。また、Salesforceの改修においてもエンジニアの方の言語化能力が非常に高く、一緒に仕事を進めやすそうだと感じました。
ーSalesforceの運用改善を推進していく中で課題を抱えていたと伺っています。どのような課題があり、松元さんはその課題をどう捉えていたか教えてください。
経営企画は、事業計画の作成と予実管理に加えて、これらを行うにあたって必要不可欠なデータ基盤の構築を担っています。私たち経営企画は、Salesforceのデータを用いてビジネスの健全性を正確に把握したり売上の要因分析や将来予測に活用したりするため、ビジネスサイドが日々のセールス活動の中で使用するSalesforceのデータの正確性は、非常に重要なものです。
そのような中で直面した最大の課題は、元となるデータの正確性の担保です。仮説や解釈が的確で、分析手法も適切であっても、元データに誤りがあれば、その分析結果は信頼に足るものではなくなってしまいます。そこでまず、基本的な指標の変動を確実になくすこと、そして、分析の粒度を細かくしてもブレない数値の管理をSalesforce上で徹底的に行う必要性がありました。
課題の原因を追求していく中で、Salesforceの基盤となるデータ構造は適切に設計されていましたが、運用面に課題があることがわかりました。解決すべき課題の優先順位と対応方法が明確になり、関係各所との調整も円滑に進んだため、具体的な改善の道筋を立てることができました。
ー課題解決のために行ったアクションとその結果どういう成果が出たのか教えてください。また、課題が見つかったとき、どのようなマインドで向き合っていますか?
経営にまつわる数値の管理は、理想的な姿を追い求めたいというのが本来の担当者としての思いです。しかし、現場の実態に即さず理想を追求するだけでは現場が回らなくなり本末転倒な結果となってしまうことは、過去に営業管理を行っていた経験から実感していました。今回のプロジェクトではそれらを踏まえ、オペレーション負荷と理想的な状態とのバランスを常に意識しながら、2つの課題解決に取り組みました。
1つ目はシステム権限の整備です。当初、Salesforceのシステム管理者の権限付与が、適切な状態でなされていませんでした。この状態ではデータの整合性が維持できないため、適切な権限管理の必要性を感じていました。そのため、各現場のオペレーションを十分に理解した上でチームごとに適切な権限サンプルを作成し、実務運用テストを実施しました。これにより、データが意図せず変更されてしまう事象を防ぎ、データ品質の維持を実現しました。
2つ目は、データ分析に必要な主要項目の要件定義の整理とデータ連携の確立です。まず、Salesforce上の各項目の定義や解釈を統一し、実績値のズレが生じる要因をセールス部門のグループマネージャーを中心とした現場メンバーと協力しながら特定していきました。そこから入力規制や自動化フローを実装することでヒューマンエラーを軽減する仕組みを実装し、施策の実施状況と収益への貢献度を常に把握できる状態を構築しました。これにより、信頼性の高いデータの分析基盤を確立することができ、事業計画のKPIの更新や現場向けダッシュボードの作成などを正確に実施することができるようになりました。

ー業務において上長や周囲の方とのコミュニケーションで、日々意識されていることを教えてください。
主に2つのことを意識していますね。
1つ目は、今何をすべきかという優先順位の判断です。自分が見えている範囲が狭い可能性もあるので、欠落しているポイントはないかを常に上長や周りの方に確認するようにしています。今自分はこういう理由でこれを優先すべきと考えているが、他に優先すべき課題はないかと、わりと頻繁にコミュニケーションを取って確認するように心がけています。
2つ目は、あらゆる事象に対して「なぜか」を考えるようにしています。なぜこういう状況なのか、なぜ今これをやらなければならないのかなど、常に物事の本質を明らかにし、関係者間で共有することで認識の齟齬が生まれないようにしています。これはもう意識しているというか、前職・前々職の上司の思考ややり方が染み付いているという感じですね。
ーSUPER STUDIOのCULTUREの中で「現場の第一人者になろう」を体現していると伺っていますが、実際に意識していることを教えてください。
SUPER STUDIOのCULTURE(行動指針)は、決して理想論的なものではなく、極めて実践的で、当たり前のことが明確に示されている印象があります。日々の業務において特別に意識して行動するというより、自然な形でCULTUREを実践できているかなと思っています。
今回のSalesforceの活用改善プロジェクトにおいても、今振り返ってみると、「現場の第一人者になろう」というCULTUREのもと、行動していたような気がしますね。システムは単なる分析ツールや業務ツールではなく、営業活動を支援し、最終的に売上につながってこそ意味があるものです。具体的な改善施策を検討する際も、現場の実態を十分に把握した上で、運用面の実現可能性を探りながら進めていきました。経営企画などのバックオフィス側にとっては理想的な改善案であっても、現場のセールスメンバーの運用において持続不可能なものであったら、それは意味を成しえません。可能な範囲で実現の可能性を図り、現場第一の視点で今回の実装を行えたかなと思っています。

ー社内外でロールモデルがいれば理由と一緒に教えてください。
前職および前々職で同じ上司の下で働く機会があり、その方から多くの学びを得ました。論理的思考力が高く、業務の目的や優先度、責任の所在を明確に示しながら的確な指示を出せる方で、私が模範とする方です。
特に印象的だったのは、業務における判断基準の明確さです。「やったほうがよい」と思われる施策がたくさんある中で、まず目的を明確にし、実施後に得られる成果と会社へのインパクト、必要な工数、現在の組織体制や人員状況との整合性、緊急性といった要素を総合的に検討して判断を下す習慣が身につきました。
また、実行すべき施策が決定した後の要件整理や進め方においても、現場などの状況に応じて何を優先し、どのようにバランスを取るべきか。なぜその判断に至ったのかという理由を明確にする能力も鍛えられたと思います。
ーSUPER STUDIO全体やグループの戦略目標を受け、今後自身が取り組んでいきたいことや目標を教えてください。
Salesforceのデータ基盤の構築は今後も継続的に進めていく予定ですが、プロダクトの利用状況のように、データ量が膨大で分析機能やコスト面からSalesforceに集約することが最適ではない領域も存在します。
そのため、中長期的にはSalesforceとそれ以外のデータを集約した統合的なデータ分析基盤の構築を計画しています。この取り組みについても、無理のない範囲で着実に実現できるよう慎重に検討して進めていきたいと思っています。
また、会社員として働く以上、会社から求められる役割に対して最適なパフォーマンスを発揮することを常に意識していきたいです。
MVPを受賞した経営企画ユニットの松元さんのインタビューをご紹介しました。これまでの経験を活かして課題を的確に捉えながらも、現場の状況を鑑みながらバランスを取って解決策を検討していくという柔軟な思考が伝わってきたと思います。業務を進めるうえでの考え方やマインドは、どんな仕事においても重要なポイントだと思いますので、ぜひ参考にしてみてください。
next
インタビュー一覧
all interview
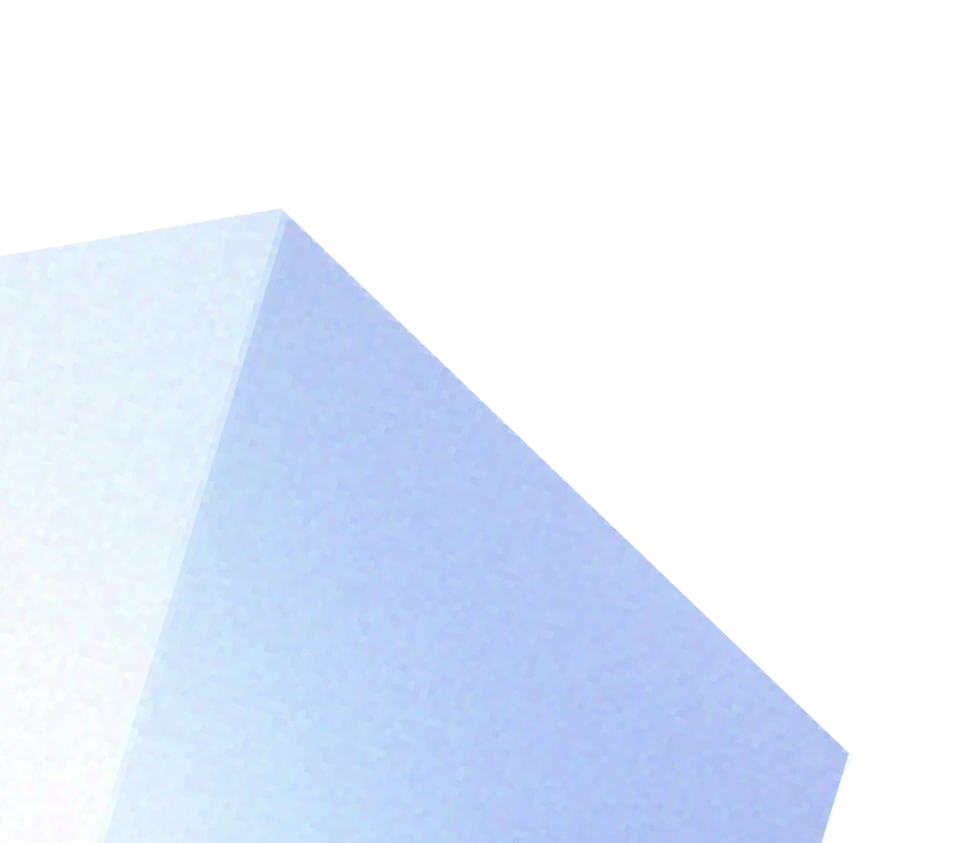
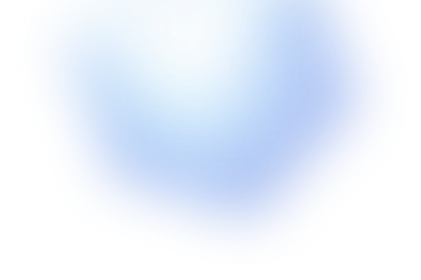
SUPER STUDIOは、心に火を灯し、ワクワクできる世の中を作るチームです。
あなたも参加しませんか?